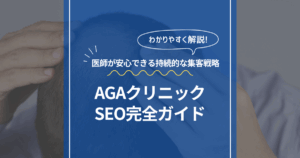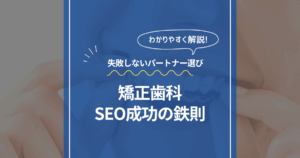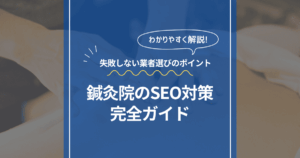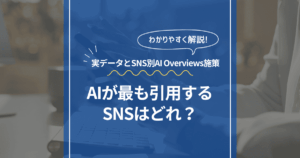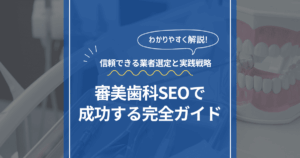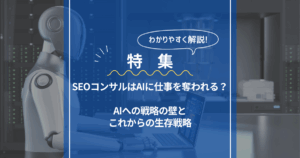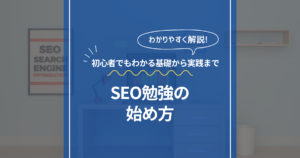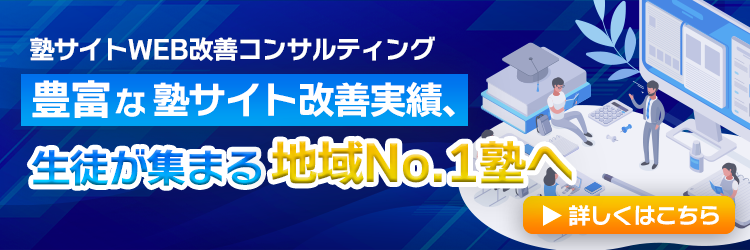記事監修の依頼方法と相場|プロが教える成功のコツ
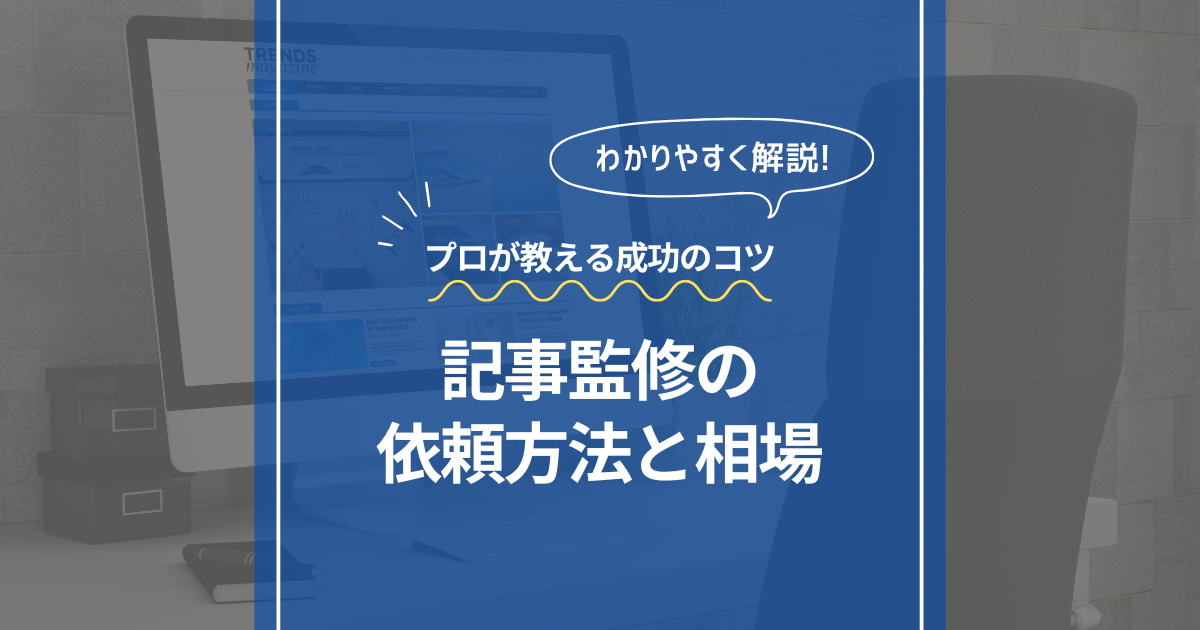
ウェブメディアの競争が活性化する中で、記事の信頼性を高める「記事監修」の重要性が増しています。
特に健康やお金に関わるジャンルであるYMYL、またGoogleの記事評価基準であるEEAT(「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」)対応においてメリットの大きい方法だと考えてください。
本記事では、記事監修の基礎知識から依頼相場、実務で使えるノウハウまで、現場で培った経験をベースに解説します。

▼ Web集客にお悩みのご担当者様へ
検索順位×売上上昇を実現する
SEO戦略を徹底解説しています。
\SEO対策の基礎から実践がわかる /
※60秒でダウンロード完了
記事監修とは?定義から依頼方法まで徹底解説

コンテンツマーケティングが主流となった現代において、記事の品質管理はWebメディアの信頼性を左右する重要な要素となっています。
特に専門性の高い分野や、正確性が求められる情報を扱う場合、適切な記事監修の実施は不可欠です。
ここからは、記事監修の基礎から実践的なノウハウまでを見ていきましょう。
記事監修の目的と重要性
記事監修とは以下のものを指します。
執筆された記事の内容を専門的な知見を持つ人物が確認し、その正確性や適切性を担保する作業
これは単なる校正や校閲とは異なり、内容の専門性や信頼性を重視したチェックプロセスです。
主な目的は、読者に価値のある正確な情報を提供することにあります。
特に医療や法律、金融などの専門分野では、誤った情報の掲載が重大な問題につながる可能性があるため、専門家による監修は極めて重要な役割を果たします。
また、Webメディアの競争が激化する中、記事の信頼性を高めることは、サイトの価値向上やブランディングにも直結します。
昨今、特にYMYL領域の信頼性担保の重要度が増しており、監修者の掲載は非常に重要な施策だと考えています。
弊社の場合、優先度最高のSランクで監修者の設置を推奨しています。
SEO観点でも最重要ですが、ユーザー目線からでも重要と考えており、例えば「抗がん剤 副作用」を調べているユーザーが閲覧しているページで、癌の権威ある医師の監修者枠が有るのとないのでは読み進める意識が全く変わってくると思います。
SEO観点でもユーザー観点でも必要な施策になります。
記事監修に必要な3つの視点
記事監修を効果的に行うためには、主に3つの重要な視点が必要です。
1.専門的正確性
2.読者目線での分かりやすさ
3.リスクマネジメント
1つ目は「専門的正確性」です。記事の内容が最新の専門知識や研究に基づいているか、業界標準や法規制に準拠しているかを確認します。
2つ目は「読者目線での分かりやすさ」です。専門的な内容を一般読者にも理解しやすい形で伝えられているか、必要以上に難しい表現を使用していないかをチェックします。
3つ目は「リスクマネジメント」の視点です。記事の内容に法的問題や倫理的な問題がないか、誤解を招く可能性のある表現がないかを慎重に確認します。
これらの視点をバランスよく組み合わせることで、質の高い記事監修が実現できます。
一般的な記事監修の手順
記事監修の標準的なフローは、大きく4段階に分かれます。
第1段階:事前準備
第2段階:監修者による内容チェック
第3段階:記事の修正
第4段階:監修者による最終確認
まず第1段階として、監修依頼前の事前準備を行います。
記事の目的や対象読者、重点的にチェックしてほしいポイントなどを整理し、監修者と共有する資料を作成します。
第2段階では、監修者による内容チェックが行われます。
この際、単なる間違い指摘だけでなく、より正確で分かりやすい表現の提案なども含まれます。
第3段階では、監修者からのフィードバックを基に記事の修正を行います。
必要に応じて監修者と協議しながら、最適な表現を検討していきます。
最後の第4段階では、修正後の内容を監修者に確認してもらい、監修完了の承認を得ます。
このプロセスを丁寧に進めることで、質の高い記事制作が可能となります。
記事監修者の選び方と相場について

記事の品質を大きく左右する監修者の選定は、慎重に行う必要があります。
適切な監修者を見つけ、継続的な関係を築くことは、質の高いコンテンツ制作の基盤となります。
ここでは、監修者選びの具体的なポイントから、実際の相場感まで、実務に即した情報をお伝えします。
監修者に求められる資格・スキル
記事監修者に求められる要件は、扱う分野や内容によって大きく異なります。
医療分野では、医師や薬剤師などの国家資格保持者が必須となりますが、一般的な商品紹介やライフスタイル記事では、該当分野での実務経験が重視されます。
専門性以外にも、重要なスキルとして「編集視点」が挙げられます。
これは、専門知識を一般読者にも分かりやすく伝えるための表現力や、誤解を招かない適切な言い回しを提案できる能力を指します。
また、デッドラインを意識した作業進行や、建設的なフィードバックを行えるコミュニケーション能力も、良い監修者の条件となります。
適切な監修者の探し方
監修者との出会い方は、大きく分けて3つのアプローチがあります。
1.マッチングサービスの活用
2.紹介
3.メディアやSNSでのアプローチ
1つ目は、専門家マッチングサービスの活用です。
医師や弁護士、税理士などの資格保持者と直接つながることができ、経歴や実績も確認しやすいのが特徴です。
2つ目は、業界ネットワークを通じた紹介です。
既存の取引先や知人からの紹介は、信頼性が高く、スムーズな関係構築が期待できます。
3つ目は、専門メディアやSNSでの発信者へのアプローチです。
ただし、この場合は監修経験の有無を慎重に確認する必要があります。
監修者を選ぶ際は、単に資格や経験だけでなく、メディアの方向性との相性や、コミュニケーションの取りやすさなども考慮に入れましょう。
現場的にも監修者探しは苦労することが多々あります。
医師やFP(ファイナンシャルプランナー)といった方は、市場に一定の人数の方がいらっしゃるので見つけることができますが、例えばtoB領域や製造業などはその領域の専門性・権威性が有る方が少ないケースがございます。
その場合は、クライアント様の社内にて、できるだけ認知があり専門性がある方に監修していただくことが多いです。
監修料の相場と決め方
記事監修の料金設定は、監修者の資格や経験、記事の専門性、作業量などによって大きく変動します。
一般的な相場としては、以下の金額が目安と考えてください。
・医師による医療記事の監修:1記事あたり2万円から5万円程度
・その他の専門分野:1万円から3万円程度
料金体系は、記事単価制の他に、月額顧問契約や時間単価制を採用するケースもあります。
特に継続的な監修が必要な場合は、月額顧問契約が双方にとって効率的な選択となることも多いでしょう。
なお、料金交渉の際は、監修作業の範囲を明確にすることが重要です。
単なる内容確認なのか、より詳細な解説の追記や修正案の提示まで含むのかによって、適切な料金は変わってきます。
また、急ぎ対応や大量の記事の一括監修など、特殊な条件がある場合は、追加料金の設定も検討する必要があることを覚えておきましょう。
記事監修でよくあるトラブルと対処法

記事監修の現場では、様々なトラブルが発生する可能性があります。
しかし、適切な予防策と対処法を知っておくことで、多くの問題を未然に防ぎ、または効果的に解決することができます。
ここでは、実際によく起こるトラブルとその具体的な解決方法について解説していきます。
監修スケジュールの遅延への対応
記事監修における最も一般的な問題の一つが、スケジュールの遅延です。
特に医師や弁護士など、本業が多忙な専門家に依頼する場合によく発生します。
この問題に対しては、予防的なアプローチが効果的です。
まず、監修依頼時に具体的な締め切りを設定し、監修者の稼働可能時間を確認します。
また、余裕を持ったスケジュール設定も重要です。
通常の監修期間に加えて、30%程度の緩衝期間を設けることで、突発的な遅延にも対応できます。
監修が遅れ気味の場合は、早めに状況確認の連絡を入れ、必要に応じて締め切りの調整や、緊急度の高い記事の優先対応を依頼するなど、柔軟な対応を心がけましょう。
監修内容との意見の相違への対処
監修者と制作側で意見が分かれるケースも少なくありません。
特に、専門的な正確性と読者にとっての分かりやすさのバランスについて、見解の相違が生じやすい傾向があります。
このような場合、まずは両者の意見の根拠を明確にすることが重要です。
監修者が指摘する専門的な観点と、制作側が重視する読者目線での分かりやすさ、それぞれの立場からの意見を丁寧に確認します。
その上で、両者の意見を活かした妥協点を探っていきます。
たとえば、専門用語を使用する際は、その直後に分かりやすい説明を加えるなどの工夫が有効です。
また、定期的な打ち合わせの機会を設けることで、監修方針の認識齟齬を減らすことができ効果的です。
クオリティ管理のポイント
記事の品質を一定水準以上に保つためには、体系的なクオリティ管理の仕組みが必要です。
まず、監修チェックリストの作成が有効です。
専門的な正確性、表現の適切性、リスク管理など、チェックすべきポイントを明確にしておくことで、監修漏れを防ぎ、効率的な作業が可能になります。
また、過去の監修履歴やフィードバック内容をデータベース化することで、よくある指摘事項や注意点を制作チーム全体で共有できます。
特に重要な指摘事項については、制作ガイドラインに反映し、記事作成の段階から品質向上を図ることが効果的です。
定期的な振り返りミーティングを実施し、監修プロセスの改善点を議論することも、長期的な品質向上につながります。
まとめ:効果的な記事監修のために押さえるべきポイント

記事監修は、Webメディアの信頼性を確保する上で欠かせないプロセスです。
本記事でご紹介した内容を実践することで、より効果的な記事監修体制を構築することができます。
ここでは、記事監修を成功に導くための重要なポイントを整理して、実務に活かせるようにまとめていきます。
特に重要なのが、記事監修の本質を理解することです。
監修は単なる校正や校閲ではなく、専門的な知見に基づいて記事の価値を高めるプロセスです。
そのため、監修者の選定は慎重に行い、その分野における十分な実務経験や資格を持つ人材を起用することが望ましいでしょう。
また、効果的な監修体制の構築には、明確なワークフローの確立が不可欠です。
事前の打ち合わせで監修基準を共有し、チェックリストを活用することで、品質の標準化を図ることができます。
さらに、監修者とのコミュニケーションを密に取り、建設的な関係を築くことで、より質の高い記事制作が可能となると考えてください。
監修料金については、業界相場を把握した上で、作業内容や専門性に応じた適切な設定を心がけましょう。
継続的な関係構築のためには、双方にとって納得のいく条件設定が重要です。
よくある質問
- 記事監修は必ず専門家に依頼する必要がありますか?
-
医療・健康、法律、金融などの専門性が高く、誤った情報が読者に影響を与える可能性がある分野では、該当分野の資格保持者による監修が必須です。一方、一般的な商品紹介やライフスタイル記事では、その分野での実務経験者による監修でも十分な場合があります。重要なのは、記事の内容に応じた適切なレベルの監修を選択することです。
- 監修料の予算が限られている場合、どのように対応すればよいでしょうか?
-
限られた予算で効果的に監修を行うためのアプローチがいくつかあります。まず、記事のリスク度や重要度に応じて監修レベルを分け、専門性の高い記事に予算を重点配分する方法があります。また、月額顧問契約を結ぶことで、1記事あたりのコストを抑えることも可能です。さらに、監修者と綿密なコミュニケーションを取り、記事作成段階から方向性を合わせることで、修正回数を減らし、コストを抑えることができます
- 監修者からの修正指示が多すぎる場合はどう対処すべきですか?
-
まず、修正指示が多い原因を分析することが重要です。記事作成者と監修者の間で、求められる品質基準や方向性の認識にズレがある可能性があります。この場合、監修基準の明確化や、事前の執筆ガイドラインの作成が効果的です。また、よくある指摘事項をデータベース化し、制作チームで共有することで、同じような修正を減らすことができます。継続的な改善のため、定期的な振り返りミーティングを設けることもお勧めします。

▼ Web集客にお悩みのご担当者様へ
検索順位×売上上昇を実現する
SEO戦略を徹底解説しています。
\SEO対策の基礎から実践がわかる /
※60秒でダウンロード完了